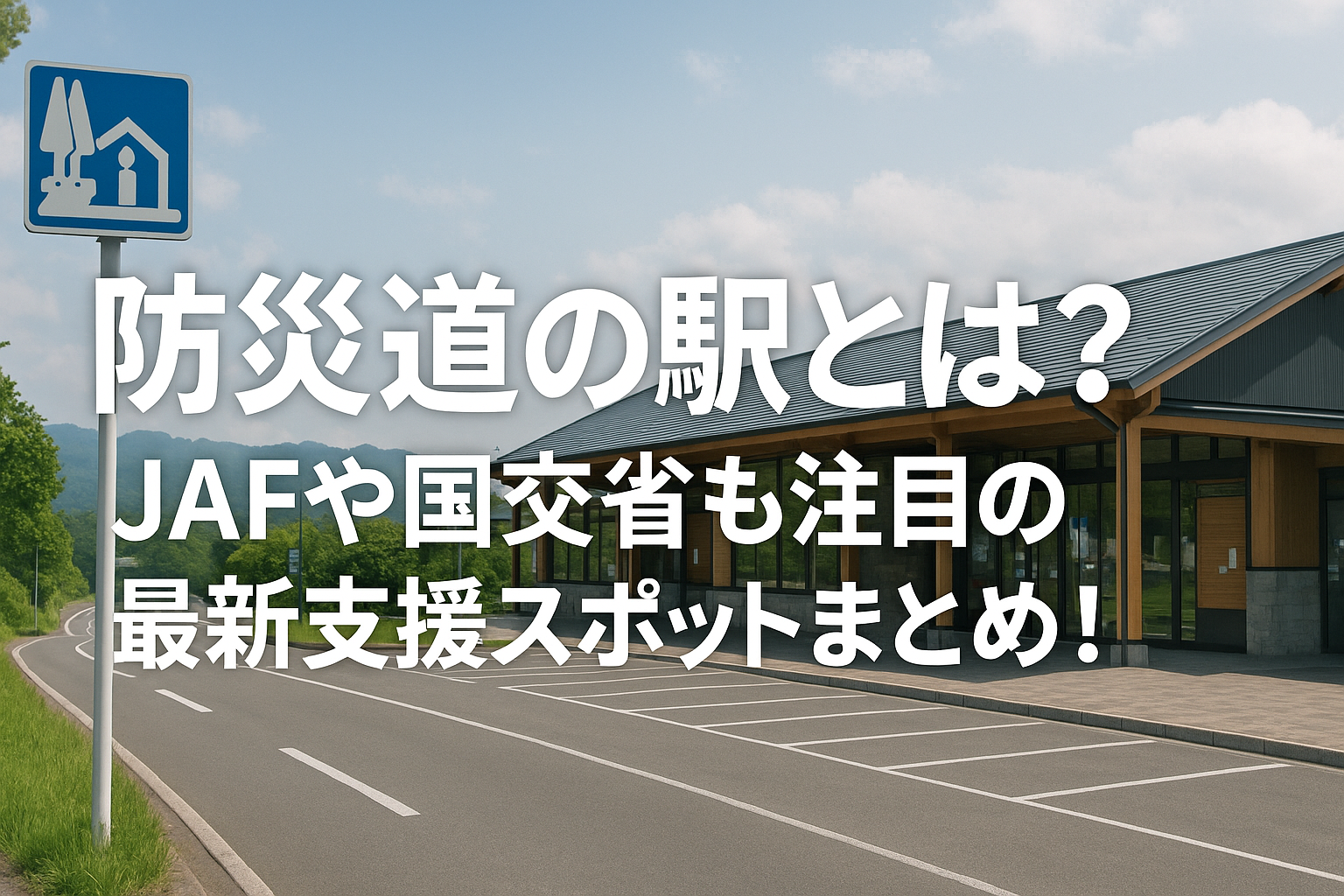「防災道の駅」って聞いたことありますか?
実は今、全国でどんどん整備が進んでいる注目の防災スポットなんです。
普通の道の駅とは何が違うのか、どんな設備があるのか、いざという時に本当に役立つのか…気になりますよね。
この記事では、2025年時点で79カ所まで拡大した防災道の駅の全貌をまるっと解説します!
JAFや国土交通省が推進する理由や、能登地震で実際に活躍したエピソード、最新の選定地域まで、気になる情報をギュッとまとめました。
こんなことがわかります👇
-
防災道の駅の定義と選定基準とは?
-
災害時に実際に役立った具体的な事例
-
現在どこにある?防災道の駅の全国一覧
-
避難や支援に活用するための基本知識とマナー
もしものとき、大切な人を守れるように。
この記事を読めば、「防災道の駅ってなに?」が「なるほど、備えておこう!」に変わるはずです✨
防災道の駅とは?国も注目するその定義と役割
近年の地震や豪雨などの自然災害に備え、全国で整備が進む「防災道の駅」。
国土交通省が主導するこの制度は、単なる休憩施設にとどまらず、災害時に地域住民や旅行者を守る“命の拠点”として注目を集めています。
この記事では、まず「防災道の駅」とは何なのか、その役割と目的をわかりやすく解説していきますね。
そもそも「道の駅」とはどんな施設?
道の駅は、ドライバーが安心して立ち寄れる「休憩・情報発信・地域連携」の3つの機能を持つ施設です。
もともとは旅の途中でトイレや買い物ができる場所としてスタートしましたが、近年では観光拠点や地域振興にも大きな役割を果たしています。
全国に約1200以上もある道の駅は、地元の特産品販売やイベントスペースとしても活用されており、地域の魅力を発信する大切な場所として親しまれています。
そんな道の駅が、次のステージとして目指しているのが「防災機能の強化」です。
普段使いの便利な施設が、災害時には避難所や支援拠点に早変わりする——そんな存在が道の駅なんですね。
「防災道の駅」としての特徴と選定条件とは?
「防災道の駅」は、国交省が地域の防災計画に基づいて選定した“防災対応力の高い道の駅”です。
例えば、広い駐車場(2500㎡以上)を持ち、災害時には支援物資の集積や避難所として活用できるようになっていることが基本条件です。
さらに、建物の耐震化や非常用電源、水や通信手段の確保など、災害時でも機能が維持できる設備が整備されている必要があります。
2021年に初めて39カ所が選ばれ、その後も対象は拡大中。2025年には79カ所に達しました。
このように「防災道の駅」は、観光と防災の両立を目指す、いわば“次世代型道の駅”なんです。
JAFや国交省が推進!防災道の駅が注目される理由
能登地震で実証された「道の駅」の防災力
2024年に発生した能登半島地震では、実際に防災道の駅の力が発揮されました。
福岡県の「道の駅うきは」に備蓄されていたコンテナ型の防災トイレが、被災地である石川県の「道の駅あなみず」へ緊急搬送され、断水に苦しむ地域で大活躍したんです。
このトイレは太陽光発電で稼働し、自己処理型で汚水も再利用できる優れもの。
このような支援がスムーズに行えたのも、「道の駅うきは」が防災道の駅としてあらかじめ準備されていたからこそ。
まさに、災害時における“地域間の連携ハブ”としての役割を果たした実例ですね。
耐震化や防災トイレなどのハード面整備
防災道の駅では、災害時でも使える施設環境の整備が最重要です。
国交省は、施設の耐震化、無停電化、貯水施設の設置、衛星電話の配備、防災トイレの導入などを重点的に支援しています。
たとえば、電力供給が止まっても最低限の照明や情報発信ができるよう、ソーラーパネルと蓄電池をセットで設置している道の駅も増えています。
また、緊急時にはドローンによる状況確認や、災害対策車両の配備を想定したスペース確保も進んでいます。
こうした「災害時でも止まらない道の駅づくり」が、JAFや国交省が力を入れる理由なんです。
最新情報!防災道の駅は全国で何カ所?どこにある?
2025年時点で79カ所に拡大!都道府県別の選定状況
2021年に初めて39駅が選定され、2025年5月には40駅が追加されて合計79駅となりました。
選定された道の駅は、駐車場の広さや耐震化の進捗、防災計画との連携などが重視されています。
たとえば、北海道の「道の駅ニセコビュープラザ」、千葉県の「道の駅やちよ」、愛媛県の「道の駅みま」など、各地に分散して設置されています。
国は都道府県単位でバランスよく整備を進めており、最終的には100駅を目標に選定が進められています。
自宅や通勤ルート、旅行先の道の駅が防災対応かどうかを確認しておくと、いざという時に安心ですよ。
山形県飯豊町の社会実験も注目!
山形県にある「道の駅いいで」は、県内で唯一の防災道の駅です。
この施設では、国の支援のもと、2カ年計画の社会実験が実施されています。
内容はとても本格的で、防災セミナー、炊き出し訓練、宿泊体験、災害車両のデモなど、実際の避難生活を想定した内容になっています。
地域住民だけでなく観光客にも開かれた参加型の取り組みで、「道の駅が災害時にどんな役割を果たせるのか」を体験を通じて学ぶ機会が用意されているんですね。
災害時の使い方ガイド!防災道の駅でできること
避難所・物資拠点・通信・仮眠スペースの活用法
防災道の駅では、以下のような利用が可能になります。
- 一時避難スペースの提供
- 飲料水・食料品の配布や販売
- 防災トイレの利用
- 携帯電話の充電や無料Wi-Fiの開放
- 災害情報の掲示・アナウンス
- 仮眠や車中泊ができるスペース確保
- 救護や医療チームの活動拠点
災害時に備えて知っておきたい利用マナー
- 必要以上のスペースを占有しない
- ゴミは必ず持ち帰る
- トイレや電源は譲り合って使う
- 職員やボランティアの指示に従う
- 個人情報の取り扱いに注意する
- ペット連れの場合は専用エリアを利用する
また、事前に防災道の駅の場所をスマホの地図アプリに登録しておくと、緊急時にも迷わず行動できますよ。
普段からのちょっとした準備が、いざという時の安心に変わります。
よくある疑問Q&A:防災道の駅についてもっと知りたい!
Q: 防災道の駅と普通の道の駅の違いは何ですか?
A: 防災道の駅は、災害時に避難所や支援拠点として機能するよう、耐震化・電源・貯水・通信設備などが整備された特別な道の駅です。広い駐車場や防災トイレなども完備されています。
Q: どこに防災道の駅があるか調べる方法は?
A: 国土交通省の公式サイトやJAFの特集ページで、全国の防災道の駅の一覧を確認できます。2025年5月時点で79カ所あり、今後も100カ所を目指して増える予定です。
Q: 災害時に防災道の駅でできることは?
A: 避難スペースの提供、飲食物の支援、仮眠、トイレ使用、携帯の充電、防災情報の取得などが可能です。災害対応に特化した設備と体制が整えられています。
Q: 防災道の駅は誰でも利用できますか?
A: はい、原則として地域住民だけでなく観光客や通行中の人も利用可能です。災害時には柔軟に対応されるので、安心して利用できます。
Q: 普段はどのように使われていますか?
A: 通常時は一般の道の駅と同じく、休憩・観光・地域交流の拠点として使われています。防災施設があるからといって利用に制限はなく、誰でも気軽に立ち寄れます。
まとめ
今回の記事ではこんなことを書きました。以下に要点をまとめます。
-
防災道の駅とは、災害時の広域避難所・物資拠点となる特別な道の駅
-
国交省が2021年に初めて選定し、2025年には79カ所まで拡大
-
JAFや自治体も注目し、実際の災害時に活躍した事例も多数あり
-
耐震化・電源・水・通信・トイレなどの設備が充実している
-
避難・仮眠・充電・情報取得など、災害時に多用途で利用可能
-
利用マナーを守ることで、多くの人にとって安心できる場所に
全国で整備が進む防災道の駅は、もはや「旅の休憩所」ではなく、いざという時に命を守る防災拠点です。
近くの防災道の駅の場所や機能を確認して、家族の防災プランにぜひ取り入れておきましょう。