2025年4月に発生したETC障害とは?

ETC障害の発生日時と対象エリア
2025年4月6日未明、ETC(自動料金収受システム)に大規模なシステム障害が発生しました。
影響を受けたのは主にNEXCO中日本が管轄する高速道路で、具体的には中央自動車道・東名高速・新東名高速などが含まれます。
今回の障害は一部の区間にとどまらず、東京、神奈川、山梨、静岡、愛知、岐阜、三重の1都6県にわたり、広範囲でETC専用レーンが利用できない状態となりました。
特にスマートインターチェンジ(ETC専用出入口)では出入りが完全にできなくなり、予定していたルートを通行できないドライバーが続出しました。
なお、NEXCO中日本によると、この障害はサーバー側の不具合とみられており、現在も調査と復旧作業が進められています。
※4月7日午後に復旧しました
ETCが使えないことで起きたトラブル
ETCレーンが使用できないことで最も大きな問題となったのが、料金所での混雑と渋滞です。
多くの料金所ではETC専用ゲートが閉鎖され、一般レーンに車両が集中。
係員による手動対応が必要となり、特に朝の通勤時間帯では長時間の渋滞が各地で報告されました。
また、スマートICの通行不可も深刻でした。
これらのICはETC専用のため、現金やカードでの通行ができず、近隣のICまで迂回しなければならないケースも。
予定より大幅に遅れる運送業者や観光客も多く、影響は個人だけでなく、物流や観光業界にも波及しています。
加えて、ETC割引が適用されない恐れがあるとの報道もあり、利用者の間では「料金はどうなるのか?」という不安の声も広がっています。
ETC障害の原因は何だったのか?

現時点で判明している障害原因
2025年4月6日に発生したETC障害について、NEXCO中日本からは現在、システムトラブルによるものという発表がなされています。
具体的な障害内容としては、料金所に設置されたETCの通信機器や中央システムとの接続エラーが起きた可能性が高いとみられています。
一部の報道によれば、ETCシステムを管理する中央サーバーとの通信障害、あるいはネットワーク機器のハードウェア不具合が原因ではないかとの見解もあります。
加えて、今回の障害では広域かつ同時多発的に不具合が発生しており、単なる機器の故障ではなく、システム全体の統合的な問題が疑われています。
現在もNEXCO中日本は詳細な調査を続けており、復旧の見通しについては「未定」とされています。
過去にもあった?ETC障害の事例
ETCのシステム障害は過去にも稀に発生していますが、今回ほど広範囲かつ長時間にわたるケースは極めてまれです。
例えば、過去には特定の料金所で一時的にETCが使えない障害があったものの、数時間以内に復旧するのが一般的でした。
これまでの事例では、機器の老朽化やファームウェア更新のミス、雷による影響などが原因でETCが一時的に停止したことがあります。
しかし今回のように複数県にまたがって数十か所以上の料金所・スマートICが同時に停止するのは異例です。
また、近年はETC2.0(高度道路交通システム)の導入が進み、システムがより複雑化しています。
その分、障害発生時の影響も大きくなっており、今後はセキュリティ対策や通信の冗長化も大きな課題となるでしょう。
ETC障害への対処法と代替策

一般レーンの使い方と注意点
ETCレーンが利用できない状況では、「一般レーン」を使うことが基本の対処法となります。
一般レーンとは、係員が常駐しており、現金やクレジットカード、ETCカードの手渡しなどによって通行料金を支払う形式のレーンです。
ETCカードしか持っていない場合でも、カードを提示すれば手動で通行処理が可能な場合が多く、慌てずに係員の指示に従うことが大切です。
ただし注意点として、一般レーンは通常よりも処理に時間がかかるため、混雑しやすい傾向にあります。
ETC専用IC(スマートIC)は完全に閉鎖されている可能性があるため、近隣の有人ICを事前に調べておくとスムーズです。
また、スマートICを利用予定だった場合は、ナビアプリなどでリアルタイムの交通情報を確認し、経路変更も検討しましょう。
ETCが使えないときの通行料金はどうなる?
ETCが使えない場合に最も気になるのが、「割引は適用されるのか?」という点です。
通常、ETCを利用すると通勤割引や深夜割引といった各種ETC割引制度が適用されますが、障害時に一般レーンを通過した場合は割引の扱いが不透明になることもあります。
今回の障害については、NEXCO中日本が公式に「ETCカードを提示した利用者については、割引が適用されるよう配慮する方針」とコメントしています。
ただし、割引処理は後日、ETC利用履歴をもとに精算されるケースもあるため、通行券や領収書は必ず保管しておくことが重要です。
また、ETCマイレージサービスを利用している場合にも、ポイントが正しく付与されるかどうかについて注視する必要があります。
疑問がある場合は、後日NEXCOのお問い合わせ窓口に連絡し、確認するようにしましょう。
今後に向けた対策と予防策はある?
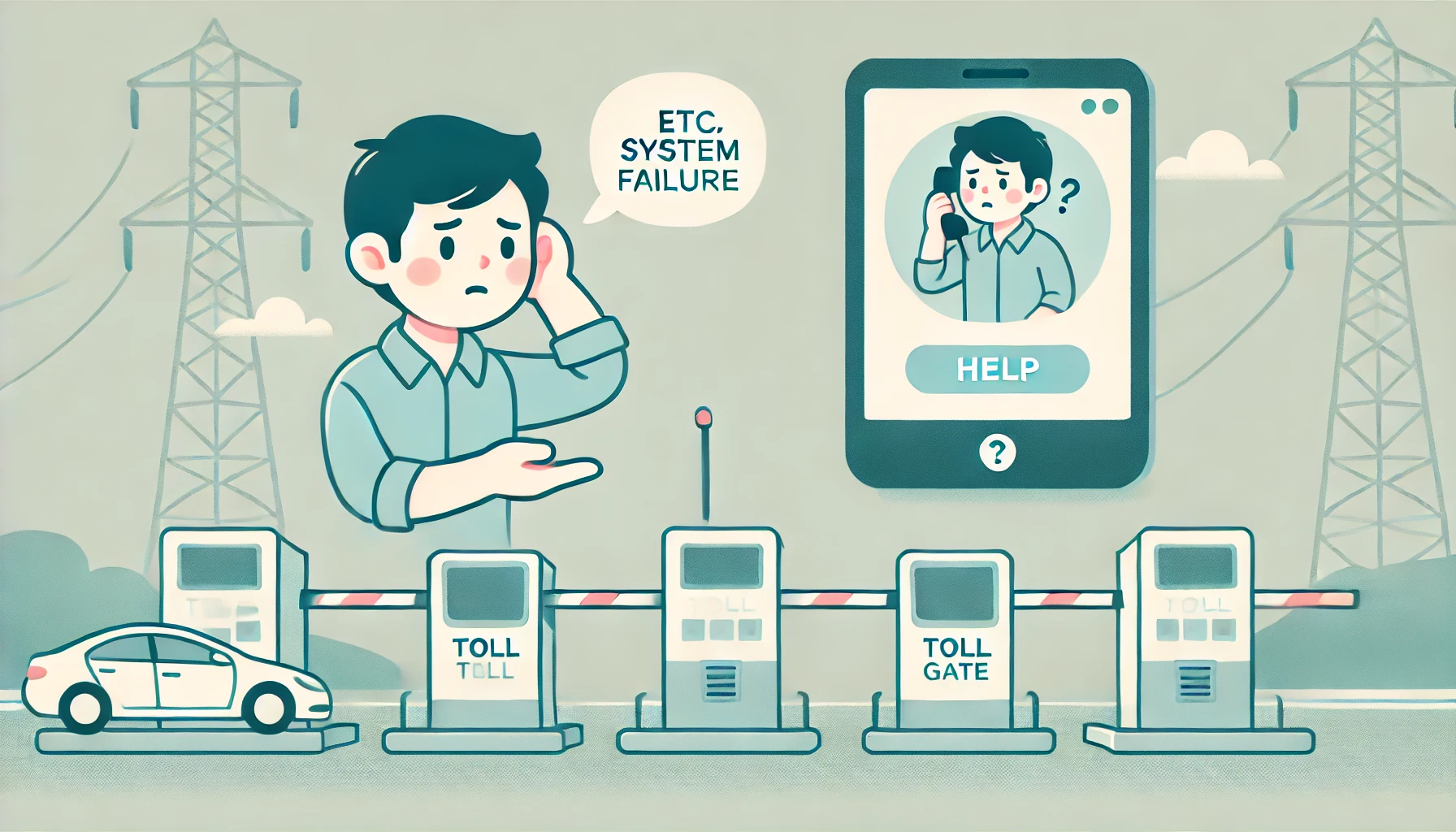
ETC障害への備えとしてできること
今回のようなETC障害が起きた際、ドライバーがパニックにならないためには、事前の備えがとても重要です。
以下のような備えをしておくと安心です。
- リアルタイム交通情報アプリのインストール(NEXCO公式・JARTICなど)
- 現金や予備の支払い手段を携帯する
- 経路周辺のIC情報を事前に確認しておく
- ETC履歴確認サイトに登録し、通行情報をチェックできるようにする
NEXCOや国の対応と今後の対策方針
今回のETC障害を受けて、NEXCO中日本をはじめとする高速道路会社や関係機関は、再発防止に向けた対策を急いでいます。
今後、予想される対策方針には以下のようなものがあります。
- サーバーや通信インフラの冗長化
- 定期的なシステム点検とアップデート
- 障害発生時の対応マニュアル整備と現場の即応体制の強化
- ドライバー向け情報提供体制の強化
テクノロジーが進化するほど便利になりますが、それに比例してトラブルの影響範囲も拡大します。
そのため、官民一体となった取り組みが今後のカギを握ります。
まとめ|ETC障害に冷静に対応しよう

2025年4月に発生したETC障害は、広範囲かつ長時間にわたる影響を及ぼし、多くのドライバーにとって混乱の原因となりました。
しかし、こうした非常事態こそ、冷静な判断と事前の備えが重要です。
障害発生時には、一般レーンの利用方法や近隣ICへの迂回、料金対応の確認が必要になります。
また、リアルタイムの交通情報を活用し、正確な情報に基づいた行動を取ることが、不要な混雑やトラブルを避けるカギとなるでしょう。
今回の事例をきっかけに、個人としても社会全体としても「高速道路インフラのリスク管理」について再認識する機会になったのではないでしょうか。
今後は、より安定したシステム運用と、万一に備えた柔軟な対応力が求められます。
