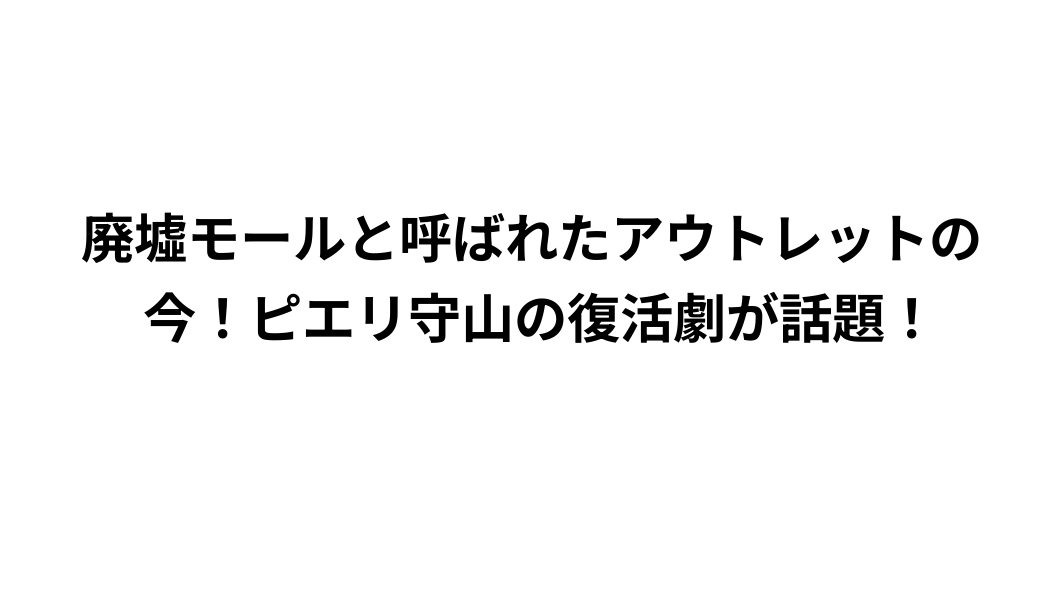最近、話題になっている「廃墟モール」って知っていますか?
一時はたくさんの人でにぎわっていたアウトレットモールが、今ではガラガラでお店もほとんどない…そんな光景が全国各地で見られるようになっています。
なかでも「明るい廃墟」として一躍有名になったのが、滋賀県の「ピエリ守山」。
でも、実はこのモール、見事に復活して今は100店舗以上が再オープンしているんです!
この記事では、
・なぜアウトレットが廃墟になってしまうのか?
・ピエリ守山はどうやって再生したのか?
・今も廃墟化が進行中のモールってあるの?
・アウトレットの未来と生き残るための条件って?
…などをたっぷり紹介していきますね。
アウトレットの今とこれからを知る、ちょっと社会派なトレンド記事です✨
廃墟モールと呼ばれたアウトレットとは?
近年、「廃墟モール」や「デッドモール」と呼ばれるアウトレットモールが増えています。
かつては多くの買い物客でにぎわっていた大型商業施設が、なぜ廃墟のように人がいなくなってしまったのでしょうか。
この章では、廃墟化したアウトレットの特徴や背景を知ることで、読者自身の街にも起こりうる問題を身近に感じてもらえるはずです。
次の見出しでは、実際にアウトレットモールが廃墟化してしまう理由について詳しく見ていきます。
なぜアウトレットモールは廃墟化するのか?
アウトレットモールが廃墟化する主な原因は、時代の流れによるライフスタイルの変化と、立地や経営方針のミスマッチです。
例えば、スマホの普及とともにECサイトで買い物する人が増え、わざわざ郊外のモールまで行く必要がなくなりました。
さらに、車離れや高齢化が進む中で、「車でしか行けない場所」にあるモールは不利になってきていますね。
加えて、同じような商業施設が近隣に乱立すると、顧客の奪い合いが起きて集客ができず、テナントも撤退してしまいます。
結果として、人の気配が消えた広大な建物がそのまま残る…これがいわゆる“デッドモール”です。
まさに“時代に取り残された”場所とも言えるのかもしれませんね。
次は、実際に日本全国で起こっている廃墟アウトレットの事例を紹介します。
全国の「デッドモール」事例を紹介
デッドモールの代表例として有名なのが「千歳アウトレットモール・レラ」です。
北海道内最大級だったこの施設も、競合の出現やコロナの影響で、現在は30以上のテナントが撤退し“ゴーストタウン化”が進んでいます。
また、愛知県の「イオンモール名古屋みなと」は、かつて賑わっていたものの競合施設との戦いに敗れ、2021年に閉館。
他にもLCワールド本巣(岐阜)やグランモール(福岡)なども、次々と空きテナントが増えた末に営業を終了しています。
こうしたモールの共通点は、地方立地・競合との競争・再生への投資不足といった要因です。
まさに「明るくて綺麗なのに人がいない」=“明るい廃墟”と呼ばれる所以ですね。
次は、そんな“廃墟モール”と揶揄された施設の中で、唯一奇跡の復活を遂げた「ピエリ守山」の事例を紹介します!
ピエリ守山の復活劇が話題に!
一時は「明るい廃墟」とまで言われたショッピングモール「ピエリ守山」が、まさかの復活を遂げたと話題になっています。
何が起きたのか?その背景を知ることで、モールが生き残るためのヒントが見えてきますよ。
まずは、ピエリ守山がなぜ「廃墟」と呼ばれるまでに追い込まれたのかを見ていきましょう。
ピエリ守山が「明るい廃墟」と呼ばれた理由
ピエリ守山は2008年にオープンし、滋賀県最大級のアウトレットモールとして華々しくスタートしました。
開業初日には5万人が来場し、周辺は「ピエリ渋滞」が起きるほどの大盛況でした。
しかし、その数年後には状況が一変。
不況の影響や周辺地域への競合モールの出現により、集客は減少。
気が付けば店舗の9割以上が閉店し、約3店舗しか残っていない状態にまで落ち込んだのです。
特に印象的だったのは、施設自体はピカピカで照明も明るく保たれているのに、買い物客も店舗もほとんど存在しない光景。
このギャップから、SNSでは「明るい廃墟」「ネオ廃墟」などと揶揄され、逆に話題となってしまいました。
かつての活気はどこへ行ったのか?
この悲惨な状況から、ピエリ守山はどうやって復活を遂げたのでしょうか?
次はその奇跡の復活劇について紹介します!
奇跡の復活!ピエリ守山リニューアルの全貌
ピエリ守山が大きく変わったのは、2014年のリニューアルです。
約10か月にわたって外観やエントランスを大規模に改装し、施設の印象を一新しました。
さらに注目すべきは、「ここにしかない体験」をテーマにしたテナントの再編です。
天然温泉「守山湯元 水春」やレイクビューが魅力のフィットネス「B-fit」、屋外アスレチック「びわこスカイアドベンチャー」など、家族や観光客が“体験”を楽しめる施設を導入しました。
その結果、2013年末には3店舗しかなかった店舗数が、リニューアル後は100店舗以上に急増!
来場者数も大幅に回復し、「廃墟」とは完全に決別しました。
ピエリ守山の復活は、“商品を売るだけ”のモールから“体験を売る場所”への転換が成功した好例といえます。
続いて、同じように廃墟化の危機に直面しながらも、復活を目指している地方モールの事例を紹介していきます!
他にもある?廃墟化から再生したアウトレット
ピエリ守山のように、廃墟と化してから復活したアウトレットモールは他にもあるのでしょうか?
全国には再生に挑戦している施設がいくつかあり、その取り組みからも多くの学びがあります。
この章では、北海道のレラをはじめとした地方モールの現在地と、再生のヒントになりうる事例を見ていきます。
北海道「レラ」や他の地方モールの現状
北海道の「千歳アウトレットモール・レラ」は、かつて新千歳空港からのアクセスの良さもあり、多くの観光客や地元客でにぎわっていました。
2005年の開業時には、道内最大級のアウトレットモールとして注目を集めていたのです。
しかし、近年は30以上のテナントが撤退し、閑散とした状態が続いています。
「休日なのに誰もいない」という声や、「ゴーストタウンみたいだった」という口コミも見られ、まさに“明るい廃墟”のような姿となってしまいました。
この背景には、競合施設の台頭に加え、コロナ禍による観光客の激減、新千歳空港からの交通アクセスの悪さといった複合的な要因があります。
地方モールの多くはこうした「一発頼みの構造」になりやすく、一度客足が途絶えると立て直すのが難しいのです。
ただし、完全に終わったわけではありません。
一部施設では地域イベントの開催や、地元企業との連携による再活性化の取り組みが始まっており、今後の再生に期待が集まっています。
次は、復活を目指すモールに共通する「再生のカギ」について紹介します!
廃墟から復活できるモールの共通点とは?
復活を遂げたモールにはいくつかの共通点があります。
最大のポイントは、「体験」と「地域性」の強化です。
ピエリ守山では、温泉・アスレチック・フィットネスといった体験型施設を導入し、ショッピング+αの価値を提供しました。
また、施設の立地特性を活かした“琵琶湖の絶景”という地域資源も上手に取り入れています。
さらに、競合との明確な差別化も重要。
どこにでもあるチェーン店ばかりではなく、「ここでしか買えない」「ここでしか遊べない」を意識した構成が成功の鍵でした。
そして、経営側の本気度も見逃せません。
店舗数が3つにまで減った中でも、10か月をかけて大規模リニューアルを実施した姿勢が、再生への流れを作りました。
こうした要素が複合的に絡むことで、再び人が集まる施設へと進化できるのです。
では、これからのアウトレットモールはどうなっていくのでしょうか?
次の章で、今後の展望と課題について詳しく見ていきましょう!
今後アウトレットはどうなる?未来と課題
これまでの事例から見えてきたように、アウトレットモールは「廃墟になるモール」と「進化して生き残るモール」に二極化しています。
この流れは今後さらに加速していくと予想されており、モール運営側にとっては大きな分かれ道です。
この章では、今まさに進行中のモールの現状と、これから生き残るために必要な要素について解説していきます。
今も廃墟化が進行中?モールの二極化とは
「廃墟化なんてもう過去の話でしょ?」と思うかもしれませんが、実は今も静かに進行しています。
現在、全国のショッピングモールの中には、稼働率が50%を切る施設も珍しくありません。
特に地方にあるモールは、人口減少や高齢化、移動手段の制限などの影響を受けやすく、若い世代が集まる都心のモールとは明暗が分かれています。
このように、都心部や人気の観光地にあるモールはますます進化し、地方モールは客足が減って“デッドモール化”していく――。
これが、ショッピングモールの「二極化」と言われる現象です。
「賑わうところはさらに賑わい、廃れるところはより廃れる」。
今後この傾向はますます顕著になると見られています。
それでは、これからの時代に“生き残るアウトレットモール”には、どんな条件が求められるのでしょうか?
生き残るアウトレットに必要な条件とは?
1つめの条件は「唯一無二の体験価値」です。
ショッピングだけでなく、温泉・アスレチック・イベント・ワーケーションなど、目的が複数あるモールは強いです。
2つめは「地域性の活用」。
地元の食材やブランドとコラボした施設や、観光と連動した施策など、その土地ならではの魅力を演出することが集客につながります。
3つめは「アクセスの良さと導線設計」。
駐車場やバス路線などの整備だけでなく、施設内の回遊性や動線も意外と重要です。
最後に大切なのは「継続的な改善・投資」です。
一度立て直しても、手を抜けばすぐに廃墟に戻ってしまう。
ピエリ守山のように、常に新しいテナントや体験を提供し続ける姿勢が問われます。
このように、ただ商品を並べるだけではもう人は来てくれません。
“選ばれるアウトレット”になるためには、魅力と戦略の両方が必要不可欠なのです。
Q&A
Q: どうして一時期は大人気だったアウトレットが、急に廃墟化してしまうのですか?
A: ライフスタイルの変化と、競合の激化が主な原因です。ネット通販の台頭、車離れ、人口減少などが重なり、郊外型モールへの来客数が激減。競合施設との集客競争にも敗れ、テナント撤退が相次ぎ、結果として“廃墟化”してしまうケースが増えています。
Q: ピエリ守山はどうやって復活できたの?
A: ピエリ守山は「体験型施設」にシフトしたことで再生しました。温泉やアスレチック、レイクビューのフィットネスなど、「ここでしかできない体験」を提供し、多様な層を呼び込むことに成功しました。
Q: 廃墟化してしまったモールは、もう再生できないの?
A: 完全に再生できないわけではありませんが、成功には大胆な改革と戦略的な再投資が必要です。地域性を活かし、差別化された体験や価値を提供できるかがカギになります。
Q: 今も“廃墟寸前”のアウトレットモールってありますか?
A: はい。北海道の「千歳アウトレットモール・レラ」など、現在もテナント撤退が続き、空き区画が目立つモールは存在します。ただし、地域イベントの開催など再生に向けた取り組みも始まっています。
Q: これからアウトレットモールはどうなっていくと思いますか?
A: 二極化がより進み、「勝ち組モール」と「廃墟化するモール」に明確に分かれていくと予想されます。生き残るには、買い物+体験を楽しめる施設へと進化することが求められます。
まとめ
今回の記事ではこんなことを書きました。以下に要点をまとめます。
-
廃墟モールと呼ばれるアウトレットが全国で増加している
-
デッドモール化の主な原因は、ECの普及・車離れ・競合増加・アクセスの悪さなど
-
ピエリ守山は「明るい廃墟」から体験型モールへ転換し復活
-
北海道の「レラ」など現在も苦戦中のモールもある
-
再生の鍵は“唯一無二の体験”と“地域性”、そして継続的な投資
買い物するだけの時代はもう終わり。
これからは「ここでしか味わえない空間体験」がアウトレットモールの命運を握る時代です。
自分の街のショッピング施設も、変化の波にどう対応していくのか、注目してみてくださいね!